こんにちは、みのりです🌿
博士課程って、研究や勉強に集中できる一方で、「生活ってどうしてるの?」「ちゃんと暮らしていけるのかな?」と、金銭面での不安を感じる方も多いんじゃないかなと思います。
私も進学を決めた当時、まわりの同期は次々と社会人になっていく中で、「自分だけお給料もないのに大丈夫かな…」とちょっぴり焦る気持ちがありました。
でも、実際に進学してみると、思っていた以上に助成金や奨学金などの支援制度が充実していて、完全に自費だけで博士課程を続けているという人には、正直ほとんど出会ったことがありません。
(※博士課程の生活スタイルや収入源は、分野や大学によって大きく異なるので、あくまで一例として読んでいただけたらうれしいです。)
今回は、そんな自分の体験もふまえて、「博士課程ってどうやって生活してるの?」という疑問にお答えできるような形で、金銭的な支援制度についてまとめてみました💡
✔ 返さなくていいお金(=奨学金・助成金)
✔ あとから返す必要があるお金(=貸与型奨学金)
✔ 指導教員の研究費で雇ってもらうRA制度 など…
それぞれの特徴や申請時期、併給できるかどうかなどもまとめています。
これから博士課程への進学を考えている方や、今ちょっと不安に感じている方の参考になればうれしいです🕊
制度の詳細や条件は年度や団体によって変更される可能性があるため、必ず公式サイトで最新の情報をご確認くださいね◎
ちなみに、「博士課程ってどんな毎日を過ごしてるの?」が気になる方は、前回の記事で私の1日のリアルなスケジュールを紹介しています👇

【もらえる支援】返還不要の奨学金・助成金
■ 日本学術振興会 特別研究員(DC1 / DC2)
博士課程に進む方の間で、もっとも有名で申請する人が多いのがこの制度です。
「学振」と略されることが多く、採用されれば生活費・研究費ともにしっかり支援される、非常にありがたい制度です✨
生活費のほかに研究費ももらえるので、自由に実験に必要なものを買ったり、海外の国際学会に参加したりできます✈️ もちろん簡単に採用されるわけではないですが、しっかり準備すればチャンスはあります。私自身もこの制度に応募して、支援をいただきながら博士生活を送っています。
- 支給額:月20万円(生活費)+年間最大150万円(研究費)
- 採用対象:
- 応募時期:
- DC1:修士2年の5月ごろ(博士進学前)
- DC2:博士1〜2年の5月ごろ(在学中)
- 併給:国費系の奨学金(JASSOなど)とは併給不可。RAなどとは併給できます。
いつかこのブログでも申請のポイントなど解説していきたいと思います!
■ 卓越大学院プログラム・次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)
学振と並んでよく名前を聞くのが「卓越大学院」や「次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)」です。こちらは各大学が独自に運営しているプログラムで、修士課程の段階から支援が受けられることが特徴。そのぶん、プログラムごとの必修授業や活動があり、研究だけに集中できるわけではないので、「自分に合っているかどうか」をしっかり見ておくのがおすすめです。
- 支給額:月最大18万円程度(大学により異なる)
- 採用対象:大学によって異なる
- 応募時期:大学によって異なりますが、大体春(4月ごろ)と秋(10月ごろ)にあります。
- 併給:他の生活費支援制度とは併給不可
卓越大学院(JSPS)
次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)
✅ 各大学が対象機関になっている必要があるため、まずは自分の大学で実施されているか確認が必要です。
■ 民間財団の奨学金
学外の財団からの助成金・奨学金にもチャレンジするという手もあります。
私の周りでも、研究分野と合っていれば積極的に申請している人が多く、採用されている人もちらほらいます✨
ここでは、特に私の身近でも貰っている人をちらほら見かける3つの財団をご紹介します。
◯ ヒロセ財団
倍率は高めで大学や専攻に条件がありますが、当てはまる方にはとても大きな支えになりますし、支援が手厚く修士1年の段階から申し込めるのも嬉しいポイントです✨
- 支給額:月30万円
- 採用対象:指定大学(東北大学、東京大学、東京工業大学、京都大学)の情報・電気・電子工学等関連分野の修士一年生、原則満 23 歳以下の日本国籍を有する者
- 応募時期:修士一年の5~6月ごろ
- 併給:他の生活費支援制度とは併給不可
◯ 日立財団 倉田奨励金
こちらも、研究分野が合っていればぜひ検討したい助成制度のひとつです。対象の分野が広く、理工系の多くの研究が該当する印象です。
財団の目的に沿った研究であることが採用のカギになるため、自分のテーマとのマッチングをしっかり確認してから応募するのがおすすめです📝
- 支給額:(1年)最大100万円/1件、(2年)最大300万円/1件
- 採用対象:エネルギー・環境、都市・交通、健康・医療で研究する45歳以下
- 併給:他の生活費支援制度とは併給不可
- 応募時期:7月ごろ
- 併給:他の生活費支援制度とは併給不可
◯ マツダ財団
マツダ財団の研究助成は、機械・電気・化学・物理といった幅広い理工系分野の研究者に開かれた助成制度です。とくに若手研究者や女性研究者の応募を歓迎しますと明記されていて、「ちょっと応募してみようかな」と背中を押してくれるような制度だなと感じます🌸
- 支給額:年間100万円
- 採用対象:機械、電気、化学、物理系。
- 応募時期:4月ごろ
- 併給:おそらく可能。詳しくは財団に確認してください。
◯ 中谷財団
こちらは、医工連携分野に取り組む大学院生向けの奨学金です。
修士課程(博士前期)から応募できる数少ない制度のひとつで、博士後期課程まで継続的に支給されるのが大きな特徴。
私の周りでも、医工系のテーマに取り組んでいる人が応募していました🧬
- 支給額:博士前期課程 月額12万円、博士後期課程 月額20万円
- 採用対象:生命科学と理工学の融合領域(医工系)に取り組む大学院生(博士前期・後期・一貫制)
- 応募時期:4月ごろ
- 併給:日本学生支援機構等、公的な奨学金との併給は可能。民間の奨学金との併給は不可。
■ RA(リサーチ・アシスタント)
RA(リサーチ・アシスタント)は、指導教員の研究費(科研費など)で雇ってもらい、研究補助などの業務を行うことでお給料を受け取る制度です。たとえば、研究室の運営や実験の準備やデータ整理、文献の取りまとめなどを手伝う形で働くことが多く、大学や業務量によって支給額は数万円〜数十万円/月ほどとさまざまです。
ちなみに、アメリカやヨーロッパでは、博士課程の学生がRA(あるいはTA:ティーチングアシスタント)として雇われて収入を得ながら学位を取るのが一般的です。
日本では、RA制度の有無や仕組みが大学・研究科によって異なり、実際に雇ってもらえるかどうかは指導教員の方針や研究費の状況によって決まることが多いです。
希望がある方は、進学前に指導教員に「RAとしての雇用の可能性があるかどうか」相談してみるのがおすすめです◎
実際に私の知り合いにも、RAの収入だけで博士生活を成り立たせている人がいます✨
- 内容:指導教員の研究費(科研費など)で雇われて、研究補助などを行う形で給与を受け取る
- 金額:大学や業務量により異なる(数万円〜数十万円/月)
- 併給:多くの場合可能
【借りる支援】返還義務のある奨学金
■ JASSO 第一種(無利子)
- 月8万円 or 12.2万円(選択制)
- 返還免除制度あり(成績優秀者など)
- 印象:無利子なので、条件が合えば負担は少なめ。中には、無利子であることを活かして「借りて運用する」という人もいます(あまり強くおすすめはできませんが…知り合いにはいます)。学振などとの併給は不可です。
■ JASSO 第二種(有利子)
- 月5〜14万円(選択制)
- 返還免除制度なし
- 印象:利子がつくため、必要性をしっかり検討してから借りるのがよさそうです。学振などとの併給は不可です。
💡 応募時期まとめ
| 支援制度 | 応募時期(目安) |
|---|---|
| 学振DC1・DC2 | 毎年5月ごろ |
| 卓越大学院・SPRING | 大学によって異なるが、大体春と夏。 |
| 財団系奨学金 | 春〜初夏に募集が多い |
| JASSO第一種・第二種 | 大学を通じて春に募集が多い |
| RA(研究室) | 随時(研究費と教員次第) |
おわりに
博士課程って、「研究に没頭できる毎日」と同時に、「本当に生活していけるのかな…」という不安もつきものだと思います。
私自身も進学前は、制度の名前だけ聞いたことはあっても「結局、何がどこまでサポートしてくれるのか?」が全然わからなくて、モヤモヤしていました。
でも実際に進んでみると、さまざまな支援制度や奨学金があって、自分の状況に合ったものをうまく活用すれば、ちゃんと生活しながら研究に向き合うこともできるんだと実感しています。
今回ご紹介した制度も、それぞれ条件やタイミングが異なるので、「どれが自分に合うか」を早めに調べておくことがすごく大切です。
もし進学を迷っていたり、不安がある方がいたら、まずは指導教員や大学の担当窓口に相談してみるのもひとつの手だと思います🌿
この情報が、少しでも博士課程への進学や生活に関する不安をやわらげるきっかけになればうれしいです🎓🌸
もしご質問や相談や感想があれば、X(旧Twitter)やお問い合わせフォームからお気軽にメッセージくださいね。


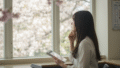
コメント